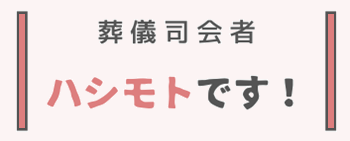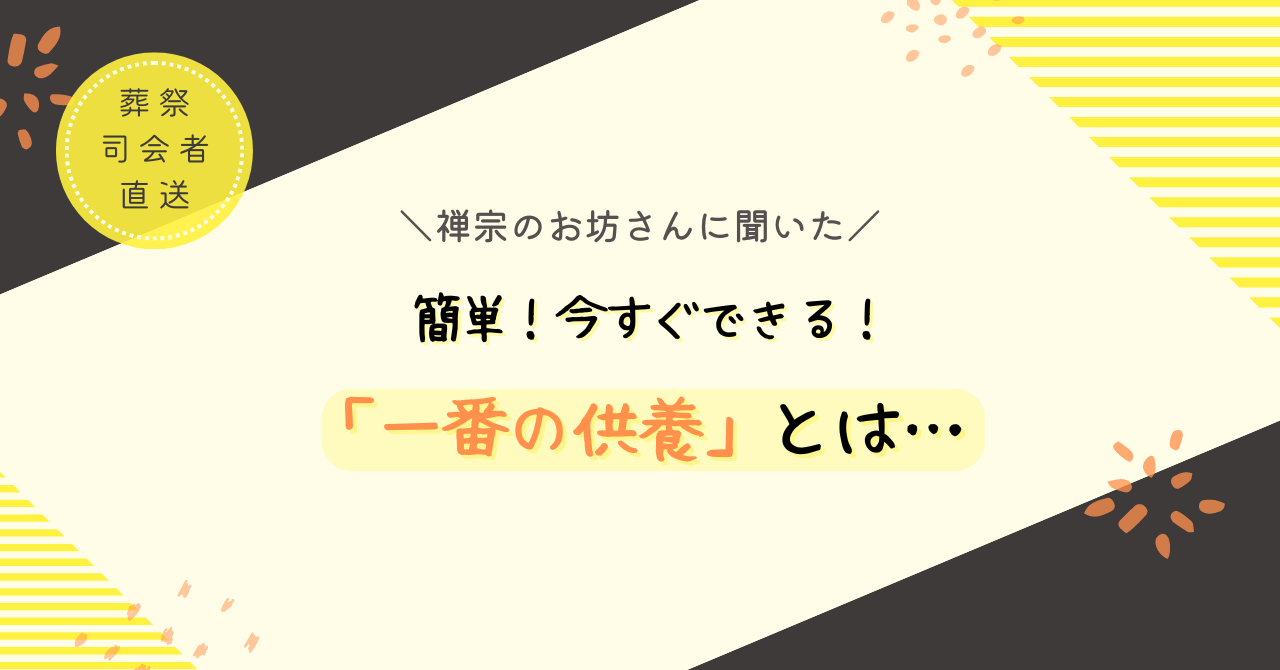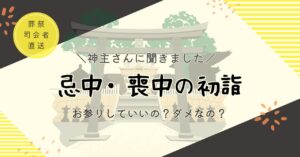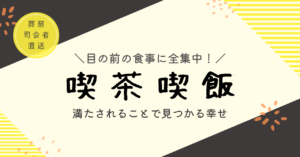私は 葬祭司会者 という仕事柄、「ご法話」を聞く機会が多いです。

「法話(ほうわ)」って何?



お坊さんのお話のことだよ!
お坊さんのお話って難しいんでしょ?と思う方もいるかもしれませんが…
そんなことはありませんよ。
根本は仏法に関する事なのですが、
子どもでも分かりやすくご法話をするお坊さんもいます。
落語家さんみたいに、面白可笑しくお話ししてくださる方も…
葬儀の場においては、亡き人とのエピソードを交えながら
心に沁みる良い話やこれからの生き方についてのご法話が多いですね。
ここでは葬儀司会者の私(ハシモト)が実際に聞いて、心に響いたご法話をご紹介していきます!
禅宗のお坊さんから聞いた「今すぐできる一番の供養」とは…
今回は禅宗の1つ「曹洞宗(そうとうしゅう)」のお坊さんから聞いたご法話を紹介します。
「一番の供養は、亡くなった人のことを忘れないことです。」
「これはいつでも、何なら 今すぐにでも出来る供養なのですよ。」
葬儀や法要の場でみんなが集まったときに故人のエピソードを話し合う。
ふとしたときに「そういえばこんな事があったな」と思い出す。
困ったときに「故人ならこんな時どうするかな?」と心に問いかけてみる。
これも全て立派な供養のカタチなのだそうです。



24時間ずっと考えていなくてもいいので、
折に触れてたまに思い出してあげて、話して共有できればもっと良いとのことですよ。
そもそも「供養」って?
「供養」を辞書などで調べると「故人にお供えなどをして冥福を祈ること」というような内容で書かれています。
私は、供養とは故人に対してだけではなく、見送った方(ご遺族)の心を癒すためでもあると思っています。
故人やご先祖を思って、お供え物をあげてローソクに火を付けて手を合わせる…
これは故人という「鏡」を通して、自分自身の心を落ち着かせる意味もある。
それは回りまわって自分にも返ってくるのだそうです。(仏教用語で「回向(えこう)」と言います)



「忌中」は「故人という鏡を通して己の心を見つめている最中だから、周りの皆さんへお気遣いできないことがあり、失礼があるかもしれませんがご容赦ください」という意味らしいです…
(所説あり)
【おまけ】供養の種類について(ざっくりと)
・「利供養(りくよう)」…食べ物やお香、花、お香、灯明などをあげる
・「敬供養(けいくよう)」…手を合わせる、お経を読む、感謝の気持ちを言葉にするなど
・「行供養(ぎょうくよう)」…故人に報告できるような生き方をする、今を一生懸命生きる



故人を忘れないでいることは「敬供養」のひとつですね!
亡き人を通して、自分自身の大切な基礎を見つめる
人はひとりでは生きられません。ご縁がある人達に助けてもらって今があります。
その中の1人が欠けても、今の自分は成り立ちません。
だからそのうちの1人がこの世を去るのは、とても辛く悲しいこと。
四苦八苦のうち、特に四苦にあたる『生老病死』は避けられない定めではありますが
みんなで一緒に大切な人を偲んで思い出して、今一度自分の基礎のひとつを見つめ直す。
=供養を通して自分自身が救われる思いもある、とお坊さんは仰いました。
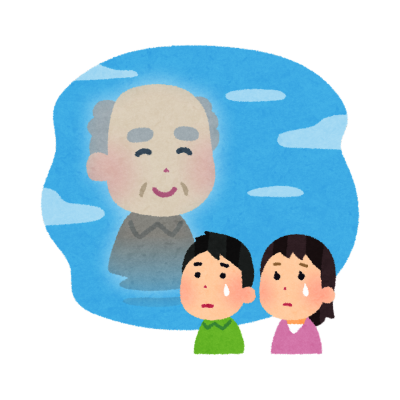
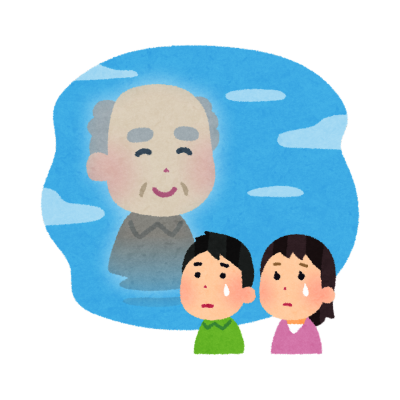
私の好きな仏教用語に「脚下照顧(きゃっかしょうこ)」という言葉があります。
お寺の玄関などに貼ってあることもあります。要は「足元に気を付けてね」って意味なのですが…
「今こうして自分が立って(存在して)いられるのは、見えていないけれど足元を支えてくれているご縁があるから。しっかり見つめて大切にしなさい。」というもう一つの意味を聞いたとき、素晴らしい教えだなと感銘を受けました。
今も大切にしている言葉です。
道元禅師「ご縁を大切に、今を生きなさい」
曹洞宗の開祖・道元禅師は「今を一生懸命に生きなさい」「沢山の人と、ご縁を刻みなさい」と教えています。
大切な人を失って心にぽっかりと大きな穴が開くような思いをすることも、人生にはあります。
故人を無理に忘れる必要はありませんよ。
私の周りでも「たまにで良いから、俺の事を思い出してほしい」と言い残して、この世を去った人がいました。
人は亡くなったら、思い出の中でしか生きられませんから…
でも振り返りすぎず、思い出を自分だけで大切にしまいこみすぎないように。
沢山のご縁に感謝しながら 今を一生懸命 生きましょう。
そして、もしあの世で再会できた時に…
「お別れしてから、私はこんなご縁をもらってこんな風に生きてきたんだよ」と、ご報告できるような生き方をしていきましょうね。
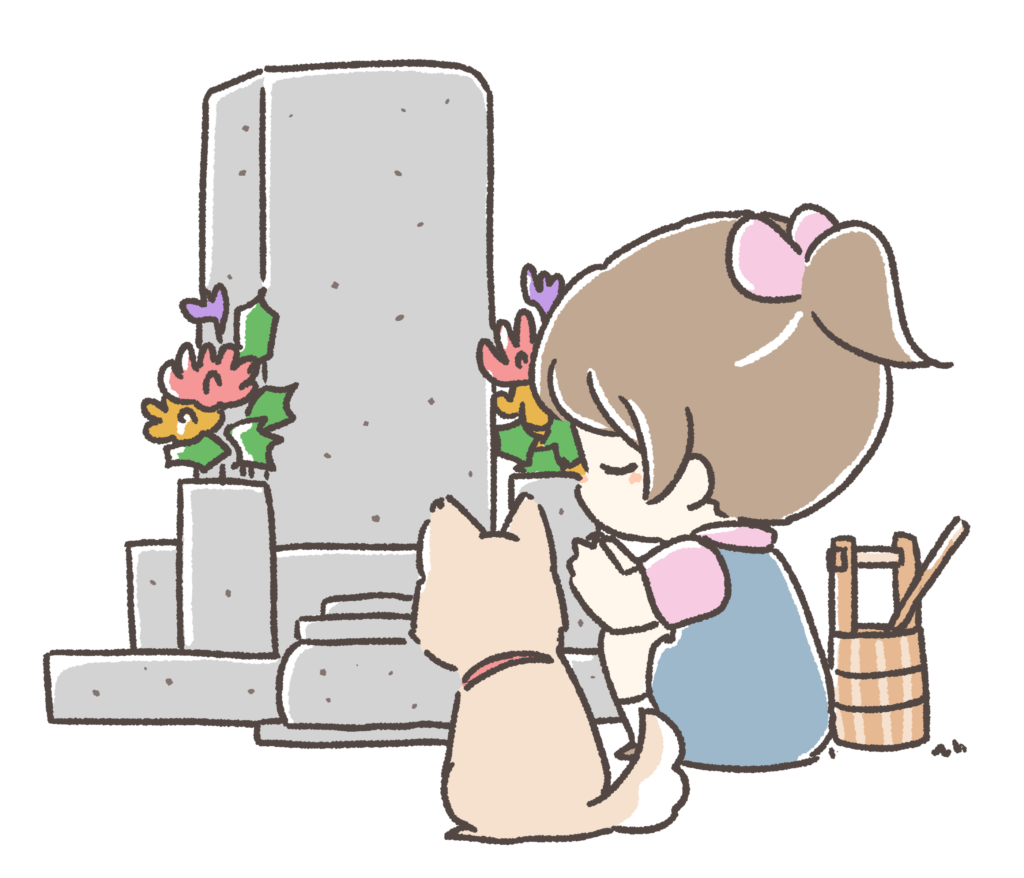
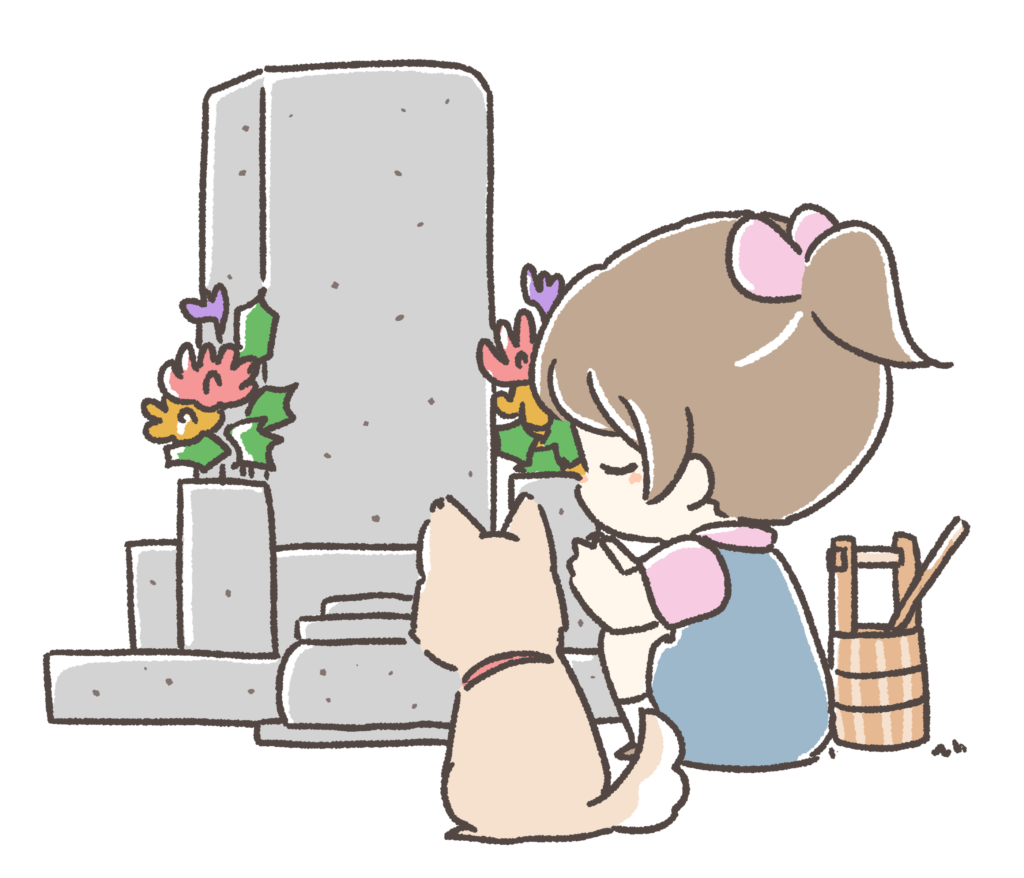
(個人が特定しないよう、一部フェイクや改変をして記事を書くことがあります。ご容赦ください。)